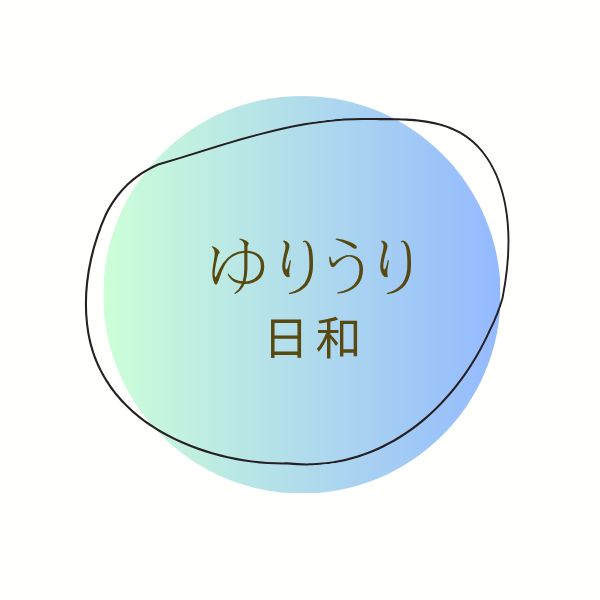※この記事はネタバレを含みます。未読の方はご注意ください。
何度かおすすめの洋書として挙げられていたため、少し難しい文学に挑戦すべく読んでみました。
正直なところ、重たい内容で何度も途中で読むのをやめようと思い、最後まで読み終えるのに2か月くらいかかりました。
いつか少女が救われるのではないかとの期待も、最後まで裏切られましたが、何故この本が評価されているのかを自分なりに見つけ出すため、何とか読み終えることが出来ました。

簡単なあらすじ(ネタバレあり)
1940年代、アメリカ・オハイオ州。
物語の中心にいるのは、黒人の少女 ペコラ・ブリードラブ。
彼女は「自分は醜い」と信じ込み、 青い目を持てば、両親も周囲の人も自分を愛してくれるはずだと願っています。
しかしペコラの現実は残酷です。 家庭では父チョリーによる暴力と、母ポーリーの無関心。 学校では容姿を理由にしたいじめ。 社会全体が、白人中心の「美」の基準を当然のものとして押し付けています。
物語の終盤、ペコラは父親から性的暴行を受け、妊娠します。 赤ん坊はほどなくして亡くなり、 彼女自身は精神的に壊れ、 「自分はついに青い目を手に入れた」と信じる世界に閉じこもってしまいます。
本の概要
- タイトル: The Bluest Eye
- 著者: Toni Morrison
- 出版年: 1970年
- ジャンル: 現代文学/アメリカ文学
- 日本語訳: 『青い眼が欲しい』(大社淑子訳 早川書房)
トニ・モリスンは、1993年にノーベル文学賞を受賞した作家。
黒人女性の歴史や声を、文学として世界に刻み続けてきました。
本作は彼女のデビュー作です。
なぜ『The Bluest Eye』は高く評価されているのか
この作品が評価され続ける理由は、 「悲劇的な出来事」そのものではありません。
① 悪役を単純に作らない構造
ペコラを傷つけたのは誰なのか。 父親? 母親? クラスメイト? 社会?
トニ・モリスンは、 誰か一人に罪を押しつける書き方をしません。
チョリー(父)は暴力的ですが、 彼自身も人種差別と貧困の中で人格を壊されてきた存在。
ポーリー(母)は娘を顧みませんが、 白人家庭で働くことでしか「自分の居場所」を感じられない女性です。
誰もが、 「加害者であり、同時に被害者」 という立場に置かれています。
この構造こそが、 物語を単なる悲劇ではなく、 社会批評としての文学へと押し上げているのではないでしょうか。
② 「青い目」という象徴の完成度
ペコラが欲しがる青い目は、 美しさ・価値・愛・承認のすべてを象徴しています。
そして舞台である1940年代は、法律上の人種差別はJim Crow法という人種差別が全米で機能していました。具体的にはトイレ、バス、学校、レストランなどで白人と黒人を分けるなど、白人優位思想が正当化されていました。
ペコラが欲しがる「青い目」も、このような差別から逃れたいと思う、あまりにも自然な願いだったのではないでしょうか。
③ 語り手クローディアの存在意義
物語の一部を語るクローディアは、 ペコラとは対照的に、 「白い人形=美しい」という価値観に違和感を覚える少女です。
彼女の視点があることで、 読者はこう問われます。
ペコラは、本当に最初から壊れていたのか?
答えは明確です。 壊れたのは彼女ではなく、 彼女を守れなかった世界。
クローディアの後悔に満ちた語りは、 読者自身の「傍観者としての立場」をも浮き彫りにします。
英語の難易度と文学的特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 難易度 | ★★★★☆(中上級) |
| 語彙 | 文学的・象徴表現が多い |
| 文体 | 詩的、時間軸・視点の変化あり |
| 分量 | 約200ページ |
文章は非常に美しく、 同時に感情を容赦なくえぐります。
また、情景が頭の中に浮かんでくる詩のような文章が印象的です。
”The sunshine dropped like honey on his head.”
“The tears rushed down his cheeks, to make a bouquet under his chin.”
英語を「理解する」より、 受け取る姿勢で読む方が、作品の本質に近づけます。
読み終えたあとに残るもの
『The Bluest Eye』は、 読み終えた瞬間に答えを与えてくれる本ではありません。
むしろ、
- なぜ彼女は救われなかったのか
- 今の社会は、本当に変わったと言えるのか
こうした問いを、 長く心に残し続けます。
まとめ
『The Bluest Eye』が名作とされる理由は、 社会が必然的に生み出した悲劇の記録いろいろな角度から表現しているからです。
この物語は、 「かわいそうな少女の話」では終わりません。
私たち自身が、 知らず知らずのうちに誰かを傷つけていないか。 美しさや価値を、無意識に押しつけていないか。
そう問い返してくる、 非常に誠実で、非常に残酷な文学作品です。
それでもなお、 読む価値があると断言できる一冊です。